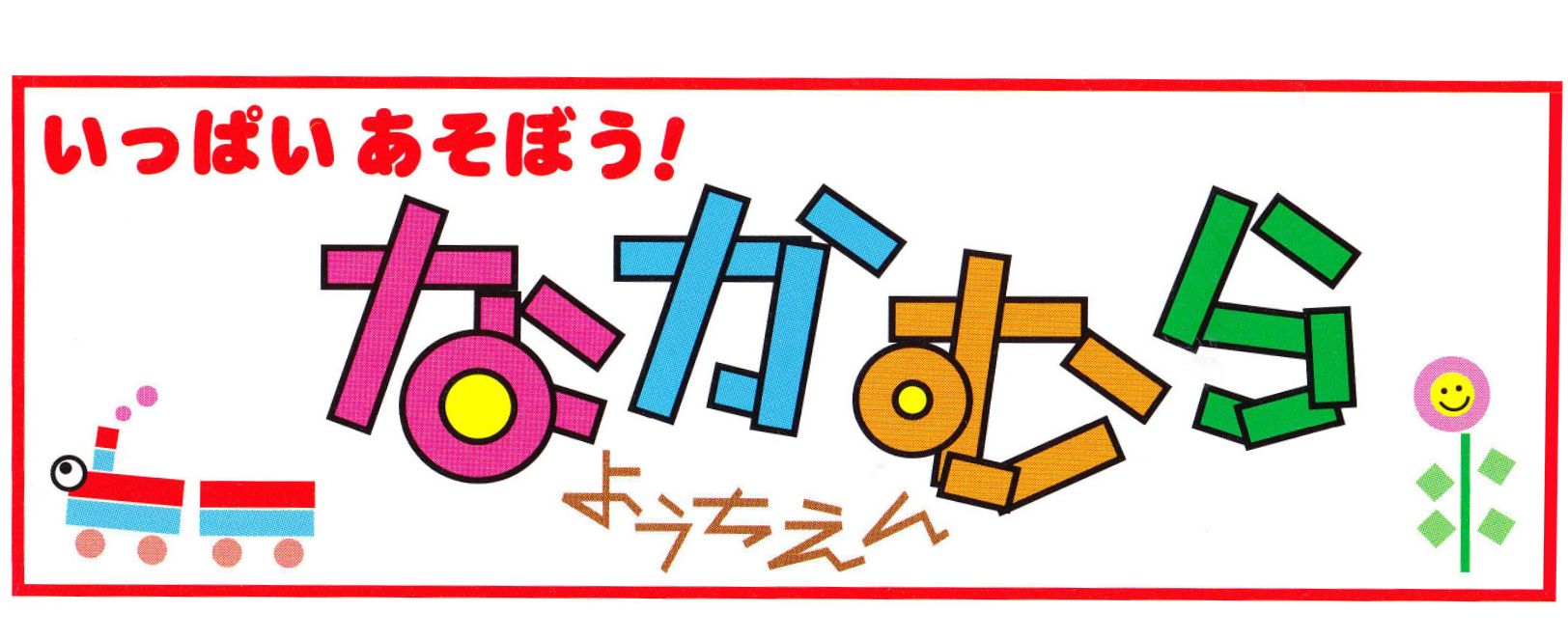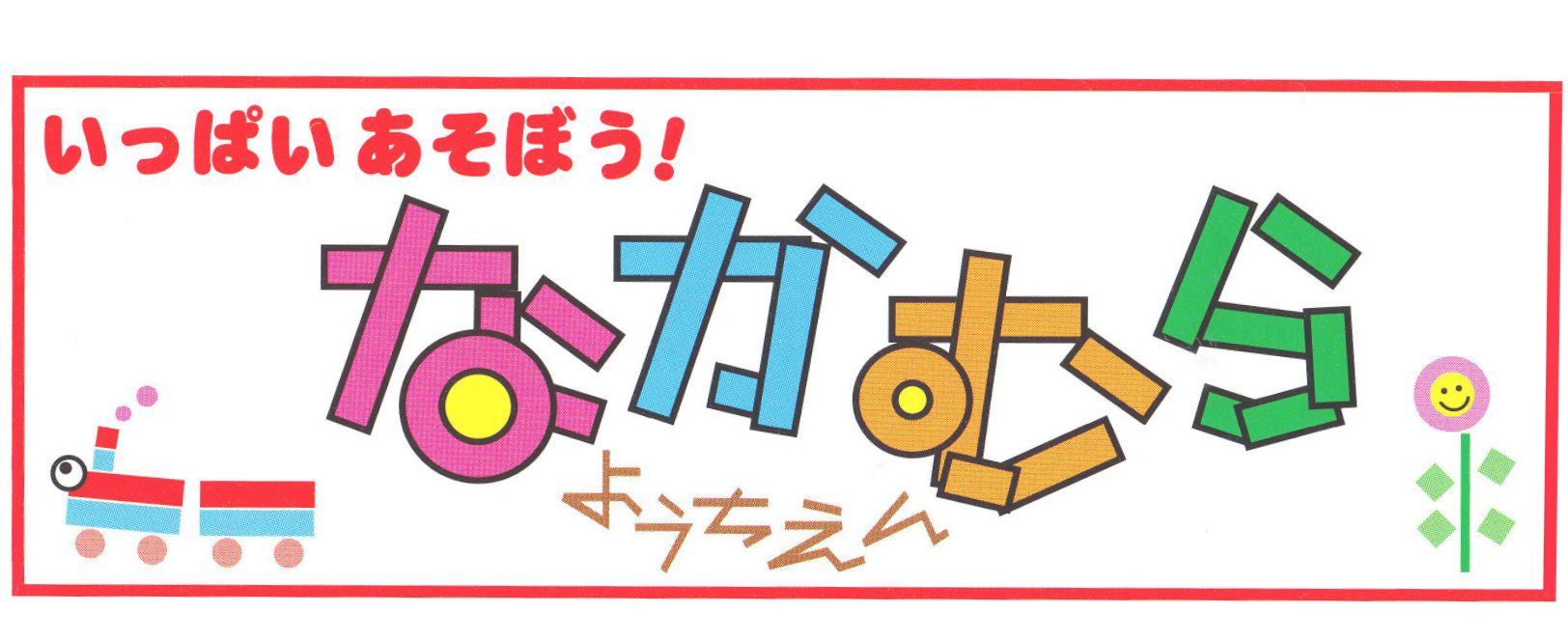Koalaのメモ「being」
幼稚園教諭で、早期発達心理士の資格を持つ荒圭子が、子育てのヒントや幼稚園での集団生活でのエピソード。幼稚園教諭の視点と同時に、母親の視点からも子育てについて記していきます。どうぞ、ご覧になってください。
ちなみに、「Koala」はKeiko Araからきています。
子育て支援だより being
令和7年4月 第10号
明日は晴れる
不朽の名作「赤毛のアン」を小3の娘と読んでいて、若い頃は「アン」やその周囲の登場人物に感情移入していたのに、いつの間にやら、マシューとマリラの気持ちもわかるようになっている自分に愕然としている今日、この頃です。この4月からはテレビアニメも始まりましたね。
さて、そんなわけで、4月です。新入園児のみなさん、入園おめでとうございます。新しい環境になるときは、子どもたちもママもドキドキですよね。
どこの園も泣き声で賑やかな4月なのですが、私達も泣きたい思いを否定せずに、心して受け止めたいと思います。
一方、ママは、子どもが赤ちゃん時代から、泣くことに対してその都度、何が原因かな・・・と対応してきましたよね。だからこそ、子どもに泣かれるとなんとなく後ろ髪ひかれる気がするものです。やっぱり、もうちょっと経ってから入園させればよかった、など、色々とママは自分自身を責めてしまうこともあるでしょう。
4月の登園からしばらくの期間は、ママや新入園児の子どもたちだけでなく、進級した子ども達も色々と葛藤する1ヶ月です。
人間というのは「慣性の動物」ですからね。
「慣性」というのは、そうです、高校時代に習った物理の「慣性の法則」からきている言葉です。「外力が加わらなければ同じ動きを続けようとする状態」です。つまり、何が言いたいかというと、人間は「慣れたところが好きだし、同じことをやり続けてしまう動物だ」ということです。だからですね、新学期の環境の変化は誰もが負担に感じるものであり、年齢が小さい子なら、脳が発達していないので、なおのこと慣れるまで時間がかかります。慣れ親しんだ環境が好きな生き物なんですから。
変化は仕方ないんです。生きていれば、いつかどこかで起こりうること。
仕方のないことなのに、子どもに嫌だとか言われると、つい、キレたくなるのですが、そこはグッと我慢して、そんな時は、子どものメンタルコーチになってみましょう。つまり、そんなときの「心の持ち方」を教えてみるんです。『変わるのって、なんかしんどいこともあるけど、でもこんなふうに考えたら?』って感じでお子さんのメンタルを支えましょう。こんなふうにのところは具体的なことが良いですね。「楽しんで」とかだと、子供って「楽しむ」ってどうすれば良いの?と途方に暮れてしまいます。
あ、お子さんによっては、アプローチの仕方を変えましょうね。あえて、ママから何か言われない方が良いというお友達もいます。特に年齢が低いお友達なんかは、ママの話を理解しているようでできていない場合があります。そんなときは、「にこやかに」送りだしましょう・・・。女優になって・・・。そうすれば、あ、色々変わったけど、ママは心配してないんだな?というのが伝わって、きっとお友達も落ち着いていくはずです。
私たちも、今は泣いちゃうこともあるけど「きっと明日は晴れる」と子ども達の力を信じています。一年前は、年少組であんなに幼かった現在の年中組の子ども達ですが、遊びに向かうパワーがすごい!その分、揉め事に向かうこともあるけど、そこは年中さんの通る道です。試行錯誤しながら友達と楽しく遊ぶ道を探っていく幼児期の第一歩が始まります。
「Google社」は、検索エンジンで有名な世界中の誰もが知る企業の一つですが、社員に最大限のパフォーマンスを発揮してもらうための大事な要素は「心理的安全性の確保」であるとしています。「不安や恐れを感じることなく、発言や質問が出来る環境や関係性」それが「心理的安全性」です。私たちも、その子の「Being」を最大限に承認することで、「心理的安全性」を確保し、子ども達がその子らしく試行錯誤できる下地を作っていきたいと思っています。
being・・・存在、生命、本質。「その子らしさ」を意味します。児童精神科医 田中哲先生考案の言葉です。
子育て支援だより being
令和6年12月 第9号
やる気よりその気
2ヶ月おきの更新を目標にしているこの「being」ですが、マルチに仕事をしているので、どうしても必要なことを先にやらねば・・・と仕事をしているうちに二学期が終わりました・・・。
この2学期は、幼稚園ではお店屋さんごっこがあったり、どんぐりが大豊作すぎて、冒険の森の斜面をふんばって歩くと「バナナの皮」でなく、まさかの「どんぐり」でツルッとすべって転びそうになって危ないという前代未聞の出来事などがあり、それに加えて、後期の子どもたちも発達もめざましいものがあるなと思わされる2学期でした。
先日はお遊戯会でしたが、普段の生活よりも意識して身体を動かすことや、自分の役割をもったり、準備や後片付けまで自分達ですることで育まれる「非認知能力」がすごいなーなどと、感じることは沢山あるのですが、それより、何より、あの、市民会館の大きな舞台で、たくさんのお客さんを前にして、笑顔で本番を迎えられた子ども達にリスペクトです。
お遊戯の練習に限ったことではありませんが、幼稚園生活の中では、教育の内容をどうするか?ということも重要ですが、子どものメンタルをどのように持って行くのかというところに、非常に心を砕きます。どのように心を砕くのかというと「やる気より、その気」になれるように、ものすごく神経を使います。
みなさん、「やる気」って常に起きますか?私は起きません・・・。
今日の夕飯の準備だって「やる気」があるからやってるんじゃなくて、追い詰められてやってます。12月といえば大掃除ですが「やる気」でません・・・。でもね、各種SNSで流れてくる、大掃除動画見てると、なんか「その気」になりますよね?それと同じです。
一人ひとりをどのように「その気」にさせて行くか・・・。これを言えば全員が「その気」になるという言葉も方法もありません。一人ひとり違った「その気」の魔法をかけながら、「その気」が主体性をもった「やる気」になるのをしっかり待つこと、それがあの大舞台での姿になっていると思っています。音楽に合わせて体を動かすことって「すべての民族は固有のダンスを持っている」と言われるように、人間のDNAに組み込まれてるなー、みんな嫌いじゃないのだなーと感じます。
つまり、何より音楽に合わせて体が動くことって理性より本能なんです。本能に突き動かされながら、一方で、人間らしい部分を使って自分をコントロールしていくこと、なんか、人間が生きるって、それの連続なのだなーと、お遊戯の練習をしながら思っていました。
中村幼稚園の子ども達は本当に「情緒が安定しているなー」と思います。
先日参加したとある講座で講師の先生が「『情緒』とは絡み合うさまざまな感情を解きほぐす糸口である」とおっしゃっていました。この二学期、幼稚園という小さな社会の中で生活することで、子ども達の中に家庭の中だけでは経験できない感情(本能の一部)が湧き上がって、戸惑うこともあったのだと思います。でも、さまざまな場面で、保護者のみなさんとお子さんが「幼稚園での日々の経験」を共有したことで、感情が糸口をみつけて解きほぐされてきました。その繰り返しが、その子の成長につながって、自信につながってきていますよ。
「自分は信頼するに足りる存在だ」、「工夫しだいでなんとかなる」、3学期も中村幼稚園らしく「あそび」でこれらを育んで行きたいと思います。
being・・・存在、生命、本質。「その子らしさ」を意味します。児童精神科医 田中哲先生考案の言葉です。
子育て支援だより being
令和6年8月 第8号
シンプルだけど深いのです
【同じ】
夕飯に珍しくハンバーグらしきものを作っていて、ひき肉をこねて形をつくっていたのですが、ハンバーグ型に丸めながら「なんか、この作業、幼稚園でもやったような・・・」と不思議な感覚だったので記憶を遡ると、「あ、そういえば、子どもたちと粘土でハンバーグ作ったんだった」と思い出して、1人で思い出し可笑しくなりました。
【シンプルに】
先日の夏祭りでは、在園児のご家族の他に、卒園児のご家族の姿もたくさん見られました。幼稚園に行ってみようとわざわざ足を運んでいただいたことが、シンプルにうれしかったです。その後の年長さんの夏季保育(お泊まり保育)では、お子さんを一晩お預かりしました。隣のお友達と笑顔を交わしながら床に着く様子を見ながら、「この子たちもたった5年前は赤ちゃんだったのだなー」と人の発達のすごさにいつも驚かされながら寝かせつけていました。
【素晴らしき保護者】
「中村幼稚園の保護者の方は、みなさんすばらしいです」と園長が毎年保護者会でお話させていただいているのですが「保護者の方がすばらしい」というのは、どのような状態なのかと言うと、例えば、園から「よく寝かせてください」とお願いすれば、多くのご家庭がお子さんのために十分な睡眠時間を作って、毎日、よく寝て体調も機嫌も良い状態のお子さんを園に送り出してくださっているというようなことです。本当にさまざまな場面で保護者の方のレスポンスが良いのです。結果、幼稚園生活が子どもの育ちによく反映されるという好循環が生まれているのだろうと思います。だからこそ、卒園しても幼稚園に連れて行ってみようと思えるのかもしれませんね。
【中村幼稚園では】
当園の保育は、系統立てられた知識を身につける「お勉強」というより、とにかく周囲の環境に自分から関わり、それらの中から、自分の五感で感じた世界の事象を自分なりに認知、判断していくこと。それと同時に、とにかく身体を動かして遊び、脳の発達の「基礎」を作るということに特化していると思っています。
ほとんどの保護者のみなさんが、そのことに気づいて「幼稚園時代はいっぱい遊ばせたい」とか「のびのび過ごしてほしい」という言葉に代表されるように、自分の子どもがこの世界で生きて行くための土台を作ってあげたいという思いをお持ちなので、中村幼稚園を選んでくださるのだと思います。
【誇り】
ともすれば、幼児期になんらかの専門性に特化した教育を受けさせたいと思っている保護者の方も少なくないこの時代に、シンプルだけど、深い考えを持って潔く中村幼稚園を選んでくださっているという事実は、私たち職員の誇りでもあります。
【3大欲求】
当園の自由遊びを観察していると、教室の入り口で「ボルダリングですか?」というくらい指先、足先をつかって扉の桟をつかんで一生懸命、並行移動して遊んでいる子をよく見かけます。心理学の分野で人間の心には「3大欲求」というのが有って、それが「自発性(自分から感)」「つながり」「有能感(できる感)」と言われています。なんというか、この「扉の桟渡り」って、この3大欲求を満たすのにぴったり・・・。(フフフ、それ面白いよね)とニヤけながら、いつも見守っているのですが、中村幼稚園の自由遊びの時間は、子どもたちが自分から心の3大欲求を満たす遊びを探して、園内中を行き交っています。時に、おもちゃが必要ないこともたくさん。その子にとって「何が遊びになるか」は、その子にしかわかりません。一見、大人から見て「遊び」とは思えないことも、よくよく観察してみると、その子にとっては重要な「遊び」の一つ。「遊び」で心が満たされているから、教室に入って先生のお話を聞いたり、少々苦手なことにも取り組んでみることができるのでしょう。もちろん、先生も自由遊び応援モードです。(あ、もちろん危ないことは止めますよ)
【来るだけで100点】
さて、二学期が始まりました。暑いから大人も子どもも毎日幼稚園に来るだけで100点ですね。水分補給を忘れずに暑さを乗り切りましょう。
being・・・存在、生命、本質。「その子らしさ」を意味します。児童精神科医 田中哲先生考案の言葉です。
子育て支援だより being
令和6年6月 第7号
DoではなくBe
先日の親子運動会を見にきていた小二の娘が、今年復活した「鯉の滝登り」を見て、「私の時には無かった!!ずるい。私もやりたかった」と騒いでいました。
親子運動会は、親子で楽しむ運動会。コロナ禍では叶わなかった競技や運営方式が元に戻って、本来の楽しい時間マシマシで行われた親子運動会。その中で行われた「鯉の滝登り」を初めて見た娘は、その競技の楽しそうな雰囲気を羨ましく感じたのでしょう。さらに、年長の保護者の皆さんと年長組の子どもたちの楽しそうな表情を目の当たりにし、娘が「ずるい」という表現になって訴えてきたことも、納得できるほど、鯉の滝登りに臨む年長さんの親子の表情が素敵な光景でした。
いつもカメラを持ち歩いている園長ですが、親子運動会ではスターターを務めています。その園長に代わり、「本番のかけっこの『ヨーイ』」のポーズをカメラに収めているのですが、一人ひとりの子の思いがあふれていて、こちらもまた素敵な光景だなーとファインダー越しに眺めています。「ヨーイ」の瞬間に感じているであろう子ども自身の心の動きが、ポジティブでもネガティブでも、「先生が受け止めてくれる!」。一人ひとりが、先生に「気持ち」も「身体」も受け止めてもらえること、そのことが心を育んでいるなーと感じさせるかけっこです。そして、ゴールでは両手を広げた先生が、走ってきた園児全員の身体も心も両手いっぱいに受け止めるのです。
この子育て支援便り「being」は「存在」「生命」「本質」という意味です。「その子らしさ」の意味で使っています。ポジティブな部分もネガティブな部分も「その子らしさ」の一部。「being(存在・生命・本質)」を全部受け止めることが、幼児期の子どもと大人との関わりの中で重要なことは、皆なんとなくわかっている、とは思うのですが、私たち大人はつい子どもの「do」(行動)にのみフォーカスして、その「do(行動)」をどうにかしようと関わってしまうのです。それだと「being(存在・生命・本質)」のやりどころがなくて、子どもはどうしていいのかわからなくなってしまうのです。「being(存在・生命・本質)」を大人に受け止めてもらいながら、自分とその周辺の世界に「年齢相応に」折り合いをつけて行くこと。そうやって、本当に自分を信じることができる子になって行くのだと思います。
決して「折り合いをつけさせる」ことが先ではありません。その子の「being(存在・生命・本質)」をマルっと受け止め、認めてあげることが先なんです。
時々「幼稚園(学校)では良い子なのに、家(家庭)ではすごいんです」というお話を聞くことがあるのですが、お家と社会で「being(存在・生命・本質)」のバランスをとっているのでしょう。それで良いんじゃないでしょうか?誰だってオンとオフがあるものです。大人も、仕事中と家庭内では多少なりとも切り替えているでしょう?子どもも、きっとそうなんですよ。
今年度私は、年少々組の子どもたちと主に関わっています。年少さん(3歳児)よりも一つ幼い、年少々さんの発達途中の「being(存在・生命・本質)」がとってもかわいい!!ひとり遊びが多く、担任を母親のように当てにし、2歳児特有のイヤイヤ期がある。でも、それが成熟した時にきっと個性を活かしながら同年代の集団の中でその子らしく生活して行くことができるのだろうと信じています。
昨年の年長さんで、お誕生会恒例の一人一人のインタビューの時「幼稚園で楽しかったことはなんですか?」と聞かれました。私たちは、これだけ遊んでいる幼稚園だから「サッカー」とか「鬼ごっこ」とかそういう事を答えるだろうなと、想像していたのですが、その子は「お勉強(ワーク等のこと)です」と答えました。きっと「僕は、皆が思っているような事ではなく、僕自身が思っていることを答えたい」という思いが強かったのでしょう。「being(存在・生命・本質)」の芽が育って、しっかりした「葉」や「茎」となっているなーと思わずにはいられない出来事でした。
自分の「being(存在・生命・本質)」を大切に受け止めてもらえた子は、他の子の「being(存在・生命・本質)」も大切にできるようになります。一人一人が他者に思いやりをもって生活できるようになることの土台が、中村幼稚園の生活にあるのです。
being・・・存在、生命、本質。「その子らしさ」を意味します。児童精神科医 田中哲先生考案の言葉です。
子育て支援だより being
令和6年3月 第6号
あゆみ
皆さん、令和5年度が終了しました。
卒園式と終業式に合わせてこの「being」を発行したかったのですが、やっぱり、間に合いませんでした。いやー、年度末、忙しかった・・・。「創造性(creativity)」というのは、ボーッとしている時間が長い方が発揮されやすいそうでやっと一仕事終え、少しのんびりパソコンに向かえるので、令和5年度最後の記事を書いています。私も皆さんも気分はもう、新学期かと思いますが、ちょっと、時を巻き戻させてください。そういうお話なので・・・。
今年もあんなに小さかった子どもたちがたくましく育って、巣立っていきました。いつの年も年長組を送りだすというのは、幼稚園にとって感慨深いものです。
3学期の初め、卒園式の歌である「さよならぼくたちのようちえん」を初めて聞いたとき「なんか悲しくなる」と呟いていた子どもたち。「悲しくなる」と言葉にしなくても、どの子もこれからくる幼稚園とのお別れのときをなんとなく感じているのが表情からわかって、側からみていて「ぐっ」とくるものがありました。
今年の卒園式の退場ソングは「旅立ちの日に」でした。
この歌は平成の卒業式の定番ですが、令和の今、新たな卒業の歌が歌われ始めているのをご存知でしょうか?主に、中高生の卒業式で歌われているそうなのですが、RADWIMPSの『正解』という歌です。卒業式の歌というより、元々は18歳という人生の岐路に立つ若者に向けた歌のようです。
18歳を30年前に通過した私で、RADWINPSのことも知らなかったのですが、楽曲が素晴らしすぎてとびました。
メロディも素晴らしいのですが、歌詞がとにかく良いのです。
はい、みなさん、じゃあまず、検索して聞いてみてください。YouTubeでにありますよ。
どうですか?聞きましたか?この『正解』の歌詞の中に
(前半略)
あぁ答えのある問いばかり教わってきたよ そのせいだろうか僕たちが知りたかったのは いつも正解などまだ銀河にもない(中略)何一つ見えない僕らの未来だから
(中略)
あぁ答えのある問いばかり教わってきたよ
だけど明日からは僕だけの正解をいざ探しにゆくんだまた逢う日まで
(後半略)
という印象的な部分があって、ここでも、職業病というか、中村幼稚園の保育が何を育み、子どもたちの人生にどう寄与しているのかを考えてしまって、今回も頭をよぎったことがありました。
それは先日お渡しした「あゆみ」についてです。
中村幼稚園の「あゆみ」は園生活の通信簿ではありません。
「あゆみ」を長らく書いていた前園長「荒美佐子」は「あゆみ」について、ママに対しては『子育てへの応援メッセージ』であり、また、子どもたちに対しては『その子の人生への励ましの言葉』なのだと私に教えてくれました。これから先の長い人生で迷うことがあっても、あなたはこんなに愛されていた、こんなに素敵なところがあったんだよという、人生の一時期を共に過ごした担任からのメッセージというのが「あゆみ」の趣旨です。
私が中村幼稚園に来たばかりの頃、卒園生だった子どもたちは今、まさに、就職活動中だったり、社会人として歩みだしていたりする年齢になっています。あの時の、あの子たちは「正解など銀河にもない問い」の中をどんな風に歩んでいるのかなーと園庭を見ながら考えています。歩みがスムーズでもそうでなくても中村幼稚園での生活が礎(いしずえ)となっていますように、と願わずにはいられません。そして、もし、ゆく手に障害物があっても「あゆみ」を見返して「自分なら大丈夫、こうやって、やって来れたんだ」と心強く思ってほしいなーと思います。
新年度、また、かわいい子どもたちを迎えます。
今は大きな制服もスモックもツンツルテンになるその日まで、子どもたちに大事なものを育んで行きたいなーと思います。
子育て支援だより being
令和6年1月 第5号
段階が変わる時
昨年末から事務仕事が次々と舞い込んで「being」のことは頭の片隅にあるのに、全然更新できずに3学期に入ってしまいました。私の拙い文章に「楽しみです」と言ってくださる保護者の方もいて、書き続けることで、保護者の方の心が軽くなったり、親子の関係が良くなったりすることがあると良いなぁと思って書いています。
年明けには大きな地震が起こり、12年前の大震災を思い出さずにはいられない被害となりました。12年前のあのとき、私は最終のバスに乗る子どもたちと事務所にいました。三月とはいえ寒かったので事務所で待っていたのです。命の危険を感じるほどの揺れに、バスに乗る前の3人の子どもたちを引き寄せて、事務所の中で姿勢を低くするのが精一杯。揺れが収まり子どもたちを園庭に避難させ、テレビをつけると大津波警報の発令、誰一人として人的被害がなかったことに胸を撫で下ろしたことを覚えています。
そんな中で、日常の有難みをひしひしと感じながらの3学期。
子どもたちの発達もフェーズ(段階)が変わってきたのが手に取るようにわかります。
息子がまだ乳児のとき、何をしても泣き止まない時があり、一体なぜなのだろうか?あれもこれもしたのに、泣き止まないなんて納得できないぞ。と思い、ネットや本で調べまくっていました。そして、最終的に納得した答えが「赤ちゃんは発達の段階が変わるときに泣くことがある」というものでした。赤ちゃんの「発達の段階が変わるとき」というのは、例えば、「昨日までぼんやりとしていた視覚が急にはっきりとして、周りのことがよく見えるようになる」とかいうようなことです。この情報を得て「あー、そりゃ、そうだ!そんな時なら泣いても仕方がないよなー。赤ちゃんは『昨日と見え方が違うからなんか不安です』」なんて言えないよね〜、泣くしかない」と納得して、泣きを受け入れたのでした。
赤ちゃんに限らず、人間の脳や体は20歳くらいまでに、どんどん発達していきます。幼稚園に在園する3年間も大きく発達します。乳児から幼児の過渡期だった年少さんは、いよいよ「幼児期」ど真ん中、幼児期ど真ん中を過ごした年中さんは「幼児期の後半」へ、年長さんは「学童期」へと発達するので、もう、幼稚園ではなく小学校がふさわしい。この時期、中村幼稚園の子どもたちの中にも確実に変化が起きています。でも、子どもの発達は右肩上がりではないのです。子どもの発達はらせん状に進みます。だんだんお兄ちゃんお姉ちゃんになってきているけど、時には、後戻りしながら大きくなっていきます。
フェーズが変わってきた子どもたち。
赤ちゃんのように泣くことはなくても、成長して、わからないことが解ってきたりすると不安になる時だってあるんです。私たちも地震や津波など自然災害の恐怖が「解った」今だからこそ、不安を大きく感じているのではないでしょうか?
中村幼稚園がブレずにいたいなあと思うのは、こんな時です。少し前の姿を思い出すと、どの子も確実に発達しています。「他の人」と比べてどうというのではなく、少し前のその子と比べてどうなのか。そこを3学期の保育の中で認めていきたいと思っています。何か、まだできないことがあっても、あなたはあなただから価値があるというメッセージが子どもたちに保育の中で伝われば良いなあと思っています。
6年生の息子の学年だよりに小学校生活も残り30日!と書かれていたので、幼稚園も数えてみました。3学期も残り24日!特に年長組は遊んで、遊んで、遊びまくって幼稚園を満喫してほしいです。この「being」も、もう一回発行できますように。
子育て支援だより being
令和5年10月 第4号
幼児期に体験させたいこと
体育フェスティバルが来ると思い出す娘のワンシーンです。
夕方、どんぐりクラブを終えて帰宅した娘(年少時)が、ガラス戸に向かって「運動会の歌」を一人で高らかに歌っている、しかも、手は後ろに組み足は開いている・・・。
今年の体育フェスティバルでは、猛暑が予想されたため、開会式のかわりに年長さんの鼓笛を行ったのですが、それ以前は開会式で「運動会の歌」を歌っていました。
年少時代の娘の歌は歌詞が間違っているけど、そこもまた年少らしくて面白くご飯の用意の手を止めてこっそり覗きみていました。
体育フェスティバルは、年長組と年中組が保育の中で行っている「体育教室」での取り組みを保護者の皆さんとシェアすることも目的にしています。
前園長の荒美佐子は「体育教室」の目的について「身体を動かすことが好きではない子も、身体を動かす楽しさを味わって、身体を動かすことを嫌いにならないため」と話していました。中村幼稚園が依頼しているカワイ体育教室の先生はプロですので、子どもの身体を楽しく動かすことにかけてはとても上手で、そこも前園長が体育教室を導入した理由と聞いています。
運動会が一年に2回というのは、そういうことが理由なわけです。
もう一つ、年長組では、同時に鼓笛隊に取り組んでいます。
鼓笛隊というと一糸乱れず演技をするというイメージがありますが、幼児期の子どもの特性から、みんなで心を一つにとか、一糸乱れずという所をゴールにするのは、大人も子どもも苦しくなるだけです。また、大人を感動させることが目的でもありません。
では、なぜ、あえて、毎年、時間をかけて取り組むのか。
中村幼稚園が、鼓笛を通して年長組の子どもたちに育みたいと思っているのは、自分の人生を生きること。「自分の人生を生きる」とは、自分で選んで、自分でやってみるということです。
幼児期の子どもたちにとって、自分の判断で何か決めてやり通すことは、大人が思うよりスリリングな体験です。大太鼓がやりたいと思っていたけど、持ってみたらすごく重たくて耐えられないから、僕は別な楽器にしようとか、本当は指揮がやってみたいけどお友達と一緒のパートが安心だから良いとか、一人ひとり、その子なりの心の動きがあります。そんな実体験から得た気づきがあるからこそ、半年間もの長い間がんばりがきくのでしょう。
本当に、どの子の判断も心の動きも尊いなあと、年長組を見ていて感じます。
毎年、体育フェスティバルの練習を共にしている私も、やはり、感動する鼓笛隊なのですが、子どもたちの演技に心動かされるのは、やはり、一人一人が、目の前のことに「思い」をもって取り組んでいるから。また、保護者の皆さんから少し離れた所で、自分で決めた「自分の人生」をいきいきと歩み始めている、そのエネルギーが大人に伝わるからなのだろうと、しみじみ思っている私です。
もうすぐ、お店屋さんごっこですね。
保護者の方がいない所でのお買い物も、スリリング体験の一つです。
あ、「スリリング」というのは前園長「荒美佐子」との会話からそのまま引用しています。
楽しい体験のなかに、少しのドキドキ感。
「スリリング」という言葉に、前園長が子どもたちに体験させたかったことが込められているなあと、年長組の作った牛乳パックロボットをみながら、例年、あたたかい気持ちになっています。おみやげ、楽しみですね!!
子育て支援だより being
令和5年8月 第3号
「いや」の本当の意味
もうすぐ、二学期ですね。
夏休みのリズムに慣れてしまって、幼稚園ってなんだっけ?って感じでしょうか。安心してください。私もです。新入園児のママも進級児のママも、今は懐かしい一学期は、お子さんの新生活を支え続けた3ヶ月だったかと思います。
先日、旧Twitterを見ていたら『子どもの「いやだ」は多義語です。』とツイートしている方がいて、そうそう!と思わず膝を打ったのですが、そのお話を・・・。
多義語というのは、読んで字のごとく「意味がたくさんある言葉」です。例えば「たこ」はお正月に飛ばす「凧」と海の生物の「蛸」という2つの意味を、私たちは状況に応じて受け取りかたを変化させます。
子どもの「いやだ」は、私たちにいつも「No」を伝えているわけではなくて、その時々でいろんな意味を持ってくるという話なのです。ある時は「わかんない」だったり、ある時は「具合悪い」って言う意味だったり、本当はいやじゃないのに、恥ずかしかったり、嬉しすぎたりして「いや」って言ってしまったり。進学進級に限らず、変化や成長に対応していく過程で、子どもたちは、時に泣いたり、暴れたり、いやいやしてみたりしながら大きくなっていく。特に、言葉を覚えて数年の子どもたちは「いやだ」をいろんな意味で使っていて、その本当の意味を、身近な大人に探ってもらい、対応してもらって人への信頼感を貯めていくのでしょう。
子どもにによっては「いや」じゃなくて「わかんない」とか「ねむい」という言葉が多義語になっているという子もいるかもしれませんね。
「いやだ」じゃなくて、もっと適切な言葉で表現してほしい、表現できるようになってほしいと考える方もいるかもしれませんが、振り返ってみると、大人だって「やばい」のひとことで色々な状態を表現することあります。ひと昔前の若者は「むかつく」その一言で全てを完結していたこともありましたね。
生まれてまだ数年の幼児期なら、言葉のレパートリーと、自分の出来事に合った言葉の選択肢が少ないので、自分の「思い」や「考え」を適切に言語化できないのはなおさらなのです。自分の思いを適切な言葉で表現し伝えることって、結構高度な作業。だから、「いやだ」の一言で済ませてしまっても仕方ないのです。
そんな時に、中村幼稚園では教員が子どもの気持ちを「代弁」してあげたり、時には、絵本など物語の力も借りながら「自分の『思い』や『考え』を、他者にわかってもらうには良い日本語があるよ」と、子どもに教えてあげたいなと思うのです。小学校に入って教科書を読むのに困らないようにとか、そういうことがメインではなく、言語化の力は、長い人生を生きやすくするツールの1つになり得ると思うから。
そんな意味で、保護者のみなさま、一学期中はご家庭でお子さんを支えていただき、本当におつかれさまで、ありがとうございました。二学期もよろしくおねがいします。
being・・・存在、生命、本質。「その子らしさ」を意味します。児童精神科医 田中哲先生考案の言葉です。
Beingとは?存在、生命、本質。 「その子らしさ」を意味します
子育て支援だより being
令和5年6月 第2号
〜「だーめーよ」〜
ある年の年少組で印象に残っている、そしてよくある場面です。
---------
A君が大好きなお気に入りのおもちゃで遊んでいます。A君の遊びは、誰がいつ見ても面白そうです。更にお気に入りのおもちゃを大切に扱うので、周りの子もそのおもちゃで遊びたくなくなってしまう気持ちが側から見ても感じ取れます。
今日もA君は、そのおもちゃで楽しそうに遊んでいます。そこにB君がやってきました。B君、そのおもちゃが気になっています。「(B君)どうするんだろう」と、付かず離れず2人を見ていると、B君がA君が遊んでいるおもちゃを取ってしまいました。A君は、B君に遊びを邪魔され、更にお気に入りのおもちゃを取られたことで憤慨し泣き出してしまいました。年少児の遊びの場面では、よく見られるやり取りです。
そんな2人のやり取りをみて、私はB君に「お友達のおもちゃを使いたい時はね、『貸して』って言うんだよ。A君に『貸して』って言ってみようよ」と提案すると素直に「かーしーて」とA君に言ってみますが、A君から返事は返ってきません。そりゃそうです。お気に入りのおもちゃを取られ、遊びが中断してしまったのですから。しかし、A君は、B君の「貸して」の願いに泣きながら「いいよ」と、B君におもちゃを貸してくれました。渋々おもちゃを貸してくれたA君ですが、「A君はきっと『まだこのおもちゃで遊びたい。できれば貸したくない』って思っているだろうなぁ。」と、A君の表情からその気持ちが手に取るようにわかりました。
そこで私はA君にこんな声をかけてみました。
「A君、お友達に貸してって言われても、貸したくない時は、貸さなくてもいいんだよ」と。するとA君は、「え?それ本当」という少しびっくりした表情で私を見返します。「A君はおもちゃ貸すの、いい?それとも、いや?」と聞くと、「いや」ときっぱり一言。A君の本心が出た瞬間です。「じゃあね、貸したくない時はお友達に『だーめーよ』って言うんだよ。B君に言ってごらんよ。」というと、少し自信なさげに「だーめーよ」とB君に対して言い換えました。
今度はB君の番です。「おもちゃ、貸してって言ったけどA君まだおもちゃで遊びたいって。だから『だーめーよ』なんだって!『だーめーよ』って言われたら、おもちゃ使えるかな?」B君は「使えない…」と返事をしおもちゃを貸してもらうのを諦めました。
そんなやり取りをして、A君は引き続き大好きなおもちゃで。B君はおもちゃを諦めて別の遊びを探しに向かいました。
----------
「貸して」ってって言われたら、快く貸してあげることも必要だとは思います。親の立場なら特に「貸してあげなさい」と言ってしまうこともあるのかなと思いますし、私も自分の子にそう言うこともありました。
でも、「貸して」の返答は「だめよ」でもいいのです。自分の本当の気持ちを口に出して言うことって大切。「貸して」って言われたら自分の本心に反して、いつでも「いいよ」って答えなきゃいけないなんて、苦しいはずです。「そんな些細なこと、いちいち教えなくても『だめよ』『いやだ』って言うでしょ」って親は思うけど、子どもって結構、親の言うこと真面目に捉えています。
親の無言の圧、感じてます。
年少児が快く「いいよ」と言えるようになるには、思う存分遊び切って、本人が満足感というか充実感を持っていることが必要不可欠です。年少児の遊びは、一人称、自分が中心です。自分の本心に逆らって「いいよ」って言ってみたり、一見親の目から見て「正しい」「優しい」と思われる行動をしてもらいたいと子どもに願うのではなく、「貸したくない時は貸さなくてもいいんだよ」と、子どもの本心を認めてあげたいと思います。特に中村幼稚園の中では。
そのような経験を繰り返すことで、今度は、「自分は我慢をして、貸してあげようか」「貸してあげなければ相手が可哀想だな」場面によっては「相手は小さい子だから、おのおもちゃで遊びたんだな」と思いやりの気持ちを持つようになるのです。自分の気持ちだけではなく、相手の気持ちや立場にも立てるようになってくるのはもう少し先の話です。
こんな経験を積んで次第に成長していき、年中、年長になっておもちゃを貸したくないと思った時はどうなると思いますか。「いまは私がこのおもちゃで遊ぶよ。あなたはこっちがいいんじゃない。これで〇〇ごっこを始めよう。」と、代替えのものを提案したり、「時々は貸してあげるけど、基本わたしの物。」と、妥協点を見い出したりして、遊びが深く展開されていくのです。これが、自分と相手の中で「折り合いをつけて遊べるようになる」ということなのです。中村幼稚園では「折り合いをつけて遊べる」と言う言葉は最大級の褒め言葉です。
「だーめーよ。」子どもの本心を隠し我慢すること、させる事が優しさの本質ではないと思うのです。
Beingとは?存在、生命、本質。 「その子らしさ」を意味します
子育て支援だより being
令和5年4月 第1号
〜在園期間で育むもの〜
入園、進級おめでとうございます。
今年から、子育て支援だよりとして「being」を発行することになりました、荒圭子です。
園内では、フリーで色々と子どもと関わったり、事務所で書類を作ったり。発達に少し遅れがあるお友達をサポートするのが仕事です。
「早期発達支援士」という資格で発達支援についての知識を少し持っています。ですので、この「being」では、子どもの姿を「しつけ」や「教育」という言葉だけで片付けるのではなく、時には子どもの行動を通訳しながら、印象に残った出来事をお伝えしていければと思います。
娘がこの春、卒園し、幼稚園で我が子の姿を見ることがなくなって寂しいのですが、先日出席した入学式では、娘の姿と共に、卒園生が誇らしげな姿で体育館に入場する姿をみて、本当によく育ったなーと感心して動画を撮っていました。
入学式後に、ある中村幼稚園ママと会った時「おなじ幼稚園出身のひいき目なのかもしれないけれど、入学式の時の中村幼稚園の子のお返事がすごく良かった」という話になりました。それも、全員。
私も動画を撮りながら同じことを思っていました。
帰宅後に動画を見直すと、それがひいき目でもなんでもなく、本当のことであることがわかります。そのママとは「一ヶ月間、卒園式の練習をしっかりやっているからなのか?」とも話したのですが、それもあるけど、「なんかもっと根本的な理由があるような気がするなー」と考えずにはいられませんでした。
慣れ親しんだ幼稚園という場所でなく、初めての「学校」という場所、大きな体育館で行われる「入学式」に、新しい先生。こんな環境に臆することなく、自己を発揮できるのは、自分に対する信頼の気持ちが育っているからなのでしょう。
「自分に対する信頼の気持ち」とはつまり、「自信」です。生まれてまだ数年しか経っていない幼児期には、生活の全てが、「自分に対する信頼の気持ち」を育んでいるといっても良いかもしれません。小さい子ですと「靴を履く」という行為でさえ、自信に繋がっている場合があります。これから幼稚園で始まる「着替え」を例にすると、「着替え」というのは、ママがやってくれるものという概念を払拭してチャレンジするところから始まります。脱ぐ、履くがスムーズになり、自分に対する信頼が確固なものになると、自立して着替えるようになります。誰でも変化が起こる時は、不安ですので、特に年少組では、担任は丁寧に不安を支えて見守ります。放っておくからできるようになるのではありません。見守られるからできるようになるのです。お弁当箱の蓋をパッキンでないものにしてくださいとおねがいしているのも、自信を育むためです。パッキンではない方が「自分でできる」の確率がとても高いですよね。
being・・・存在、生命、本質。「その子らしさ」を意味します。児童精神科医:田中哲先生の言葉です。